つながるファブリーコミュニティ
患者さんとご家族の声

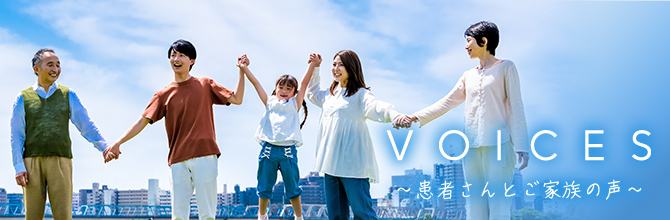
患者と医療者がともに考え、診療方針を選択することの安心感
ファブリー病と診断されたとき、当面、治療しないことを選択。数年後、飲み薬が承認されたタイミングで治療を始めました。診断から治療開始までのあゆみと医療者への思いについて、お話を伺いました。
四肢疼痛の原因が明らかになり、気持ちはすっきり
ファブリー病の症状は、いつ頃からみられたのでしょうか?
小学校高学年頃から、手足の痛み(四肢疼痛)がありました。体育の授業で長距離走をすると手足に不快感が残ったものの、当時は病気という意識はまったくありませんでした。
痛みは次第に強くなり、中学生のときに母に相談したところ
「自分も思春期の頃に同じような痛みを感じていたし、
体質的なものかもしれない。30歳くらいになったら自然に
治るから」と。実際、成長するにつれて少しずつ痛みが薄らいでいきましたので、こういうものかと思っていました。
小学校高学年頃から、手足の痛み(四肢疼痛)がありました。体育の授業で長距離走をすると手足に不快感が残ったものの、当時は病気という意識はまったくありませんでした。
痛みは次第に強くなり、中学生のときに母に相談したところ「自分も思春期の頃に同じような痛みを感じていたし、体質的なものかもしれない。30歳くらいになったら自然に治るから」と。実際、成長するにつれて少しずつ痛みが薄らいでいきましたので、こういうものかと思っていました。
ファブリー病と診断されるまでの経緯を教えてください。
きっかけは、10年ほど前に母が突発性難聴を訴えたことでした。いくつかの病院を受診した末に、現在私が通院している病院でファブリー病と診断されました。難聴はおそらく、
ファブリー病によるものだろうということでした。そのときに現在の主治医でもある循環器内科の先生が「同じ症状
(四肢疼痛)を経験している娘さん(私)も、ファブリー病の可能性があります」と母に伝えてくださったことから、
私も受診することになりました。
受診前にインターネットで病名を調べてみると、自分が経験してきた症状が書かれていました。「私もファブリー病だろう」という確信がありましたので、受診するなり自分から「遺伝子検査をしてください」と依頼しました。
検査によって診断が確定したわけですが、薄らいでいたとはいえ当時も疼痛は残っていましたので、その原因が明らかになり、治療法があることもわかったことで、気持ちはすっきりしました。
きっかけは、10年ほど前に母が突発性難聴を訴えたことでした。いくつかの病院を受診した末に、現在私が通院している病院でファブリー病と診断されました。難聴はおそらく、ファブリー病によるものだろうということでした。そのときに現在の主治医でもある循環器内科の先生が「同じ症状(四肢疼痛)を経験している娘さん(私)も、ファブリー病の可能性があります」と母に伝えてくださったことから、私も受診することになりました。
受診前にインターネットで病名を調べてみると、自分が経験してきた症状が書かれていました。「私もファブリー病だろう」という確信がありましたので、受診するなり自分から「遺伝子検査をしてください」と依頼しました。
検査によって診断が確定したわけですが、薄らいでいたとはいえ当時も疼痛は残っていましたので、その原因が明らかになり、治療法があることもわかったことで、気持ちはすっきりしました。
当面は治療しないことを選択
すぐに治療を始められたのですか?
診断された当時、ファブリー病の治療法としては酵素補充療法がありました。先生からは治療をすすめられたものの、
考えた末にお断りしました。仕事が忙しく、週末に予定が入ることも多かったため、2週間ごとの通院と数時間の点滴を
継続することは難しいと思いました。また、私は小さい頃から病院や注射がとても苦手でしたので、先生に「当面は治療をしたくありません」と正直に伝えました。
診断された当時、ファブリー病の治療法としては酵素補充療法がありました。先生からは治療をすすめられたものの、考えた末にお断りしました。仕事が忙しく、週末に予定が入ることも多かったため、2週間ごとの通院と数時間の点滴を継続することは難しいと思いました。また、私は小さい頃から病院や注射がとても苦手でしたので、先生に「当面は治療をしたくありません」と正直に伝えました。
治療を行わないことについて、医師とはどのような話をされたのでしょうか?
当然「治療すべきだ」と言われるだろうと覚悟していました。ですが、私が「当面は治療をしたくありません」と伝えると、先生は、この先、症状がどのように進行する可能性があるか、また、治療開始はどのタイミングが望ましいか、といったことを医学的見地から丁寧に説明した上で、当面は治療しないという私の意思を受け入れてくださいました。
私は大変驚きましたが、先生は「ファブリー病の治療は生涯
続くものであるため、患者本人が十分に納得してから始めるべき」という考えをお持ちのようでした。また、当時の治療法は酵素補充療法のみでしたが、近い将来、飲み薬の登場が見込まれていた時期でもありました。飲み薬が登場すれば、仕事を含めたライフサイクルに合わせて治療法を選択することが可能になります。そのときに改めて治療について
考えてみてもいいのではないか、というお話もしていただきました。
当然「治療すべきだ」と言われるだろうと覚悟していました。ですが、私が「当面は治療をしたくありません」と伝えると、先生は、この先、症状がどのように進行する可能性があるか、また、治療開始はどのタイミングが望ましいか、といったことを医学的見地から丁寧に説明した上で、当面は治療しないという私の意思を受け入れてくださいました。
私は大変驚きましたが、先生は「ファブリー病の治療は
生涯続くものであるため、患者本人が十分に納得してから
始めるべき」という考えをお持ちのようでした。また、
当時の治療法は酵素補充療法のみでしたが、近い将来、
飲み薬の登場が見込まれていた時期でもありました。飲み薬が登場すれば、仕事を含めたライフサイクルに合わせて
治療法を選択することが可能になります。そのときに改めて治療について考えてみてもいいのではないか、というお話もしていただきました。
飲み薬の承認後、治療を開始
治療を開始するまでの経緯を教えてください。
診断後の数年間は、血液検査などのために1年に1回のペースで通院していました。飲み薬の開発状況については先生から逐次伺っていましたし、自分でも調べていました。最初に
欧州で承認され、その2年後に日本でも承認されて先生から「日本でも、飲み薬での治療が可能になりますよ」と連絡をいただいたときは、とてもうれしかったですね。
診断後の数年間は、血液検査などのために1年に1回のペースで通院していました。飲み薬の開発状況については先生から逐次伺っていましたし、自分でも調べていました。最初に欧州で承認され、その2年後に日本でも承認されて先生から「日本でも、飲み薬での治療が可能になりますよ」と連絡をいただいたときは、とてもうれしかったですね。
その時点で、疼痛の症状はどのような状況だったのでしょうか?
日常生活ではほぼ感じなくなっていて、風邪を引いて発熱したときなどにうっすら痛みを感じる程度でした。飲み薬による治療に関して、先生からはメリットとデメリットを
とても丁寧に説明していただいたのを覚えています。薬がどのように作用するのかを、私にも理解できるように教えてくださいました。
日常生活ではほぼ感じなくなっていて、風邪を引いて発熱したときなどにうっすら痛みを感じる程度でした。飲み薬による治療に関して、先生からはメリットとデメリットをとても丁寧に説明していただいたのを覚えています。薬がどのように作用するのかを、私にも理解できるように教えてくださいました。
治療を始めることに対して、不安はありましたか?
母が先行して飲み薬を服用していましたので、私も早く始めたいと思っていました。不安よりも期待のほうが大きかったと思います。
母が先行して飲み薬を服用していましたので、私も早く始めたいと思っていました。不安よりも期待のほうが大きかったと思います。
治療の意義について、医師からはどのような説明を受けたのでしょうか?
先生からお話しいただいた治療の目的は、将来的な聴覚障害、心疾患のリスクを少しでも下げるため、ということでした。また、家系内に、心疾患などのために平均寿命よりも
10~15歳も若い年齢で突然死してしまった親族がおり、
このまま治療を受けないでいると自分もそうなってしまう
かもしれないというイメージがありました。
そのため飲み薬による治療を始めることへの抵抗感はあまりなく、服用を習慣づけることさえできれば長期間継続できるだろう、と考えていました。
そのため飲み薬による治療を始めることへの抵抗感はあまりなく、服用を習慣づけることさえできれば長期間継続できるだろう、と考えていました。
先生が私の意思を受け入れてくれたから、通院を継続できた
患者さんと医療者がともに考え、診療方針を決めるシェアード・ディシジョン・メイキング(Shared Decision Making;SDM)という意思決定の方法について、どのようにお考えでしょうか?
私にとって、治療を始めるタイミングを先生と相談しながら決めることができたのはとてもよかったと思っています。
診断時に「当面は治療しない」と決めたものの、それでよいのだろうか?という不安は少なからずありました。ですが、先生と定期的に会って飲み薬の開発状況を聞くだけでも
安心することができました。患者側の意思や希望と、医学的見地に基づく医療者側の意見とをすり合わせながら診療方針を決めていくほうが安心できるという患者は、私だけではないと思います。
最終的に診療方針を決めるのは患者だとしても、その決断にまったく迷いがないというケースは少ないはずです。
私が点滴による治療を受けないと決めたとき、先生が
その意思を受け入れてくださらなかったら、今の私は医療とつながっていないかもしれません。先生が私の意思を受け入れてくださり、将来のことを相談できたからこそ通院を続けられましたし、飲み薬が承認されたとき、すぐに治療を
始めたいと決断できました。
ファブリー病の治療は生涯にわたって続き、その過程では
さまざまなライフステージを経験します。各ライフステージで最適な判断を行う上で、患者と医療者がともに考え、
診療方針を決めるSDMの手法は有効だと思います。
私にとって、治療を始めるタイミングを先生と相談しながら決めることができたのはとてもよかったと思っています。診断時に「当面は治療しない」と決めたものの、それでよいのだろうか?という不安は少なからずありました。ですが、先生と定期的に会って飲み薬の開発状況を聞くだけでも安心することができました。患者側の意思や希望と、医学的見地に基づく医療者側の意見とをすり合わせながら診療方針を決めていくほうが安心できるという患者は、私だけではないと思います。
最終的に診療方針を決めるのは患者だとしても、その決断にまったく迷いがないというケースは少ないはずです。
私が点滴による治療を受けないと決めたとき、先生がその意思を受け入れてくださらなかったら、今の私は医療とつながっていないかもしれません。先生が私の意思を受け入れてくださり、将来のことを相談できたからこそ通院を続けられましたし、飲み薬が承認されたとき、すぐに治療を始めたいと決断できました。
ファブリー病の治療は生涯にわたって続き、その過程ではさまざまなライフステージを経験します。各ライフステージで最適な判断を行う上で、患者と医療者がともに考え、診療方針を決めるSDMの手法は有効だと思います。
関連資料
患者さんが医療者とともに決める診療方針
